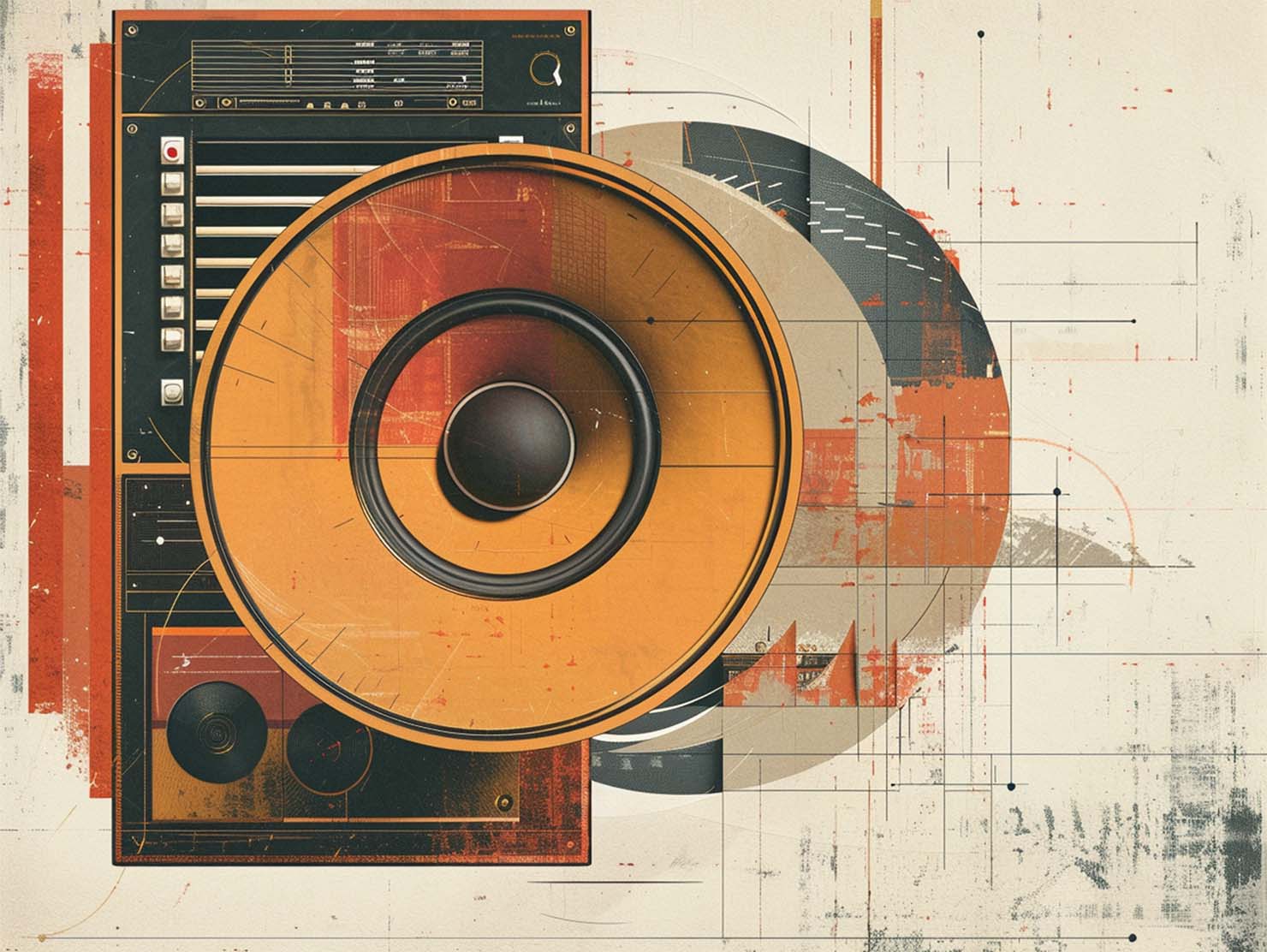スピーカーの発音体=ユニットとは、電気の信号を音に変える装置です。 アンプから送られてくる電気信号がこの装置に届き、中のボイスコイルと呼ばれる部品が振動して音が再生されます。 スピーカーユニットは個別に購入可能で、スピーカーを一から作る場合やユニットのみを交換したい場合に役立ちます。
前回はユニットの種類やその名称、音の仕組みについてをご紹介しました。
今回はドロンコーンやウーファーの形状、センターキャップの役割について、オーディオライターの炭山アキラさんに解説していただきます。
磁気回路を持たないユニット「ドロンコーン」
先にご紹介したユニット群は、「フレミングの左手の法則」で電気信号を音波に変えるための「磁気回路」を持っていますが、磁気回路を持たないユニットもあります。
スピーカーの大半は、ウーファーから出る低音の一番下の方(ローエンドと呼ぶ)を伸ばすため、バスレフ(bass reflex)という形式のキャビネットを採用しています。 キャビネットへあけた穴の奥へ装着した筒(バスレフダクト)によって、ウーファーそのものの低音より低い周波数を出し、上手くつなぐことで最低域を伸ばす方式です。

そのバスレフダクトに代わって用いられるのが、磁気回路を持たないユニット、ドロンコーンです。 バスレフダクトは、キャビネット内の空気容量とダクトの断面積、長さで共鳴周波数を決めますが、ドロンコーンは振動板の重さを変えることによって、共鳴周波数が変わります。
なぜただの筒でバスレフが構成できるのに、わざわざコストのかかるユニットを使うのか。 バスレフは、ダクトからどうしてもユニット裏側の音が漏れ出しやすいものです。 ドロンコーンだってそれが皆無とはいいませんが、ただの筒よりもずっと少なくすることができ、それだけ高品位な音の再生を望むことができる、ということです。


ドロンコーンにも、パッシブラジエーターという別名があります。 磁気回路を持たないというだけで、別にこの働きはコーン型以外でも果たせるものですから、平面振動板などもありました。 それでドロンコーンとはいいにくいユニットも出てきたから、というのが別名誕生のきっかけじゃないかな、と推測しています。
ちなみに、ドロンコーン(drone cone)とは「なまけもののコーン」、パッシブラジエーター(passive radiator)は「受動的な振動板」くらいの意味です。 ドロンコーンとバスレフには、他にもいろいろな利害得失があるのですが、ここで解説すると長くなるので、また稿を改めたいと思います。
ウーファーの形状
ウーファーは、すり鉢のような斜面と中心部に丸いドーム型のキャップを持った「コーン型」の振動板が圧倒的多数です。 というか、スピーカーユニット全体でも圧倒的主流なのがこの形状です。
コーン型の派生として、センターキャップが巨大で、すり鉢状の斜面が外周上に少し残った格好の「セーラーキャップ型」というものもあります。 水兵さんの帽子に形が似ていることから名付けられました。
また、センターキャップが前向きに出っ張っているのではなく、凹んだ形状の「コンケーブ型」(concave = 凹んだ)もあります。 2024年7月に発売されたオーディオテクニカ『AT-SP3X』のウーファー部分がそれです。
コーン型のすり鉢斜面には、メガホンのような「ストレート・コーン」と、複雑な曲面構成を持つ「カーブド・コーン」があります。


ストレートの方が絶対的な強度は高く、限られた帯域をしっかりと鳴らす必要がある、ウーファーへ用いられることが多い形状です。 一方のカーブド・コーンは、強度はストレートに譲りますがチューニング次第で分割振動をコントロールしやすく、ワイドレンジの再生が求められるフルレンジへ、多く採用されます。
また、コーンの深さもいろいろあり、深い方が強度が取れる分ウーファーに、浅い方が分割振動させやすいからフルレンジに、それぞれ向くことが多いようです。
センターキャップの役割
センターキャップは、磁気回路へゴミが入らないようにするダストカバーの役割に加え、全部ではありませんが、高域方向の再現性へ密接な関係を持っているユニットが多いものです。

特に高域まで再生することが求められるフルレンジでは、分割振動が2次、3次と高度化していき、最高域はほとんどボイスコイルそのものから音が出ている、という状態になっています。 そしてそれは、そのままではピーク性の強い、あまり洗練されていない音といわざるを得ません。
そこでセンターキャップは、ボイスコイル周辺をカバーすることで、鋭いピークを抑えて聴きやすい音にする、という効果を得ているものがあります。
一方、ボイスコイルへセンターキャップを直付けして、より積極的にトゥイーター的な鳴り方をさせているユニットもあります。 これを、コーン型振動板+センターキャップのドーム型振動板ということで、「メカニカル2ウェイ」と呼ぶこともあります。
センターキャップの形状もさまざま
フルレンジの中には、センターキャップの代わりに「サブコーン」と呼ばれるお猪口のような出っ張りが設けられているものがあります。 これもセンターキャップと同じく、ピークを抑えたり積極的に高域を鳴らしたりするためのものです。 メインコーンとサブコーンを持つことから、こういうユニットを「ダブルコーン型」と呼ぶこともあります。

コーン型はウーファーやフルレンジへの採用が多い形式ですが、スコーカーやトゥイーターなどにも広く用いられています。 それだけ長年のノウハウが蓄積していることに加え、先に説明した斜面形状や深さなど、設計の自由度が高いことも好感されるところなのでしょう。
Words:Akira Sumiyama