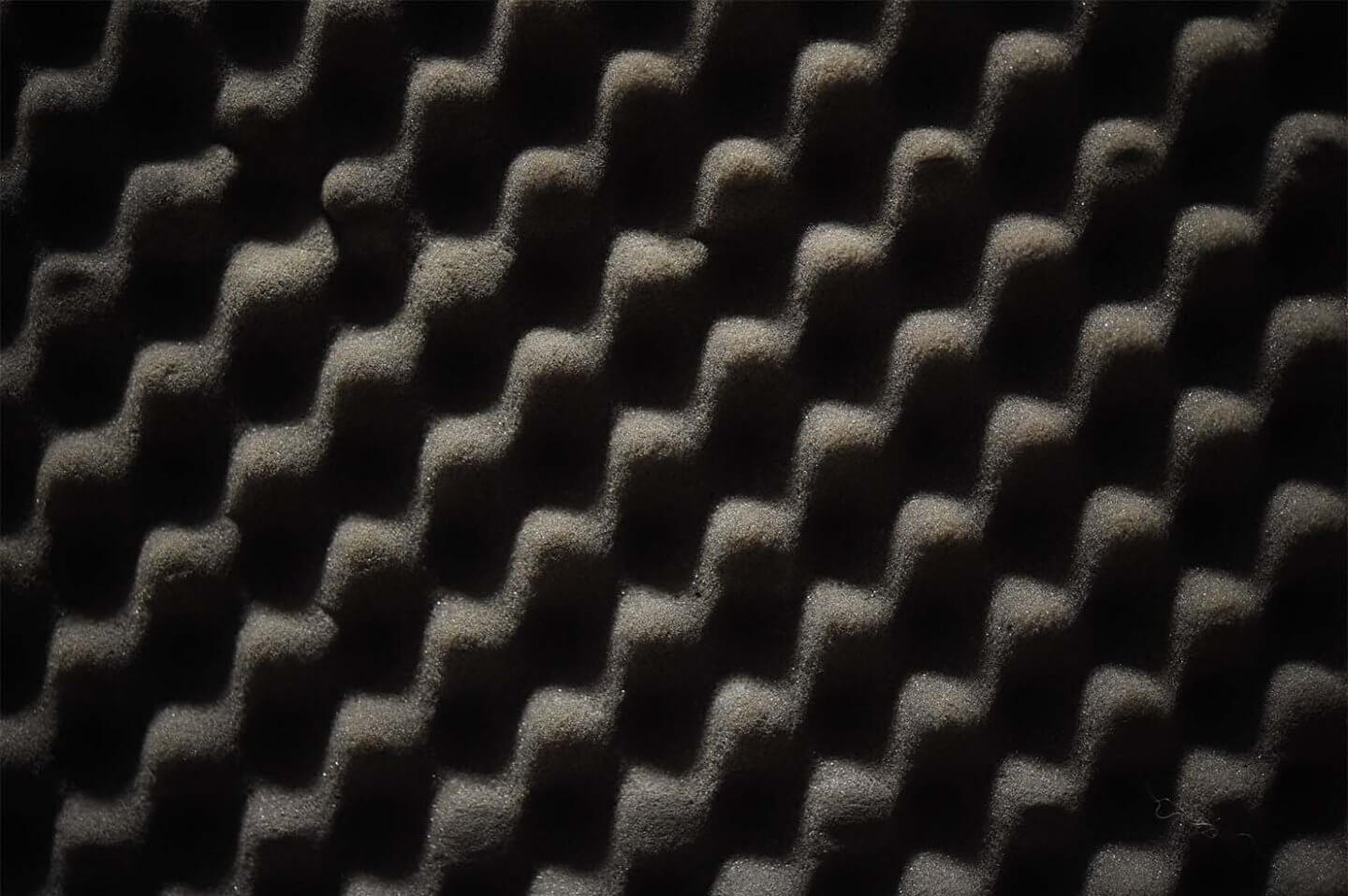知っているようで知らないスピーカーの「吸音材」について、スピーカーの設計や製作もこなすオーディオライターの炭山アキラさんが解説する本企画。 前編では吸音材の役割や素材の種類と特徴について紹介いただきました。 後編となる本稿では、炭山さんが自作したリファレンススピーカーにおける吸音材の扱いのほか、吸音材の設置テクニックをご紹介します。 スピーカー自作派の方はぜひ参考にしてください。
スピーカー自作派には「吸音材」を“使わない”選択肢もある
これまで数々のメーカー製スピーカーの内部をのぞいてきましたが、吸音材が使われていない製品は一つとしてありませんでした。 ならば、吸音材は絶対に必要なものなのかというと、私はそうでもないと思っています。
2000年に亡くなられた、オーディオ評論家でスピーカー工作の巨匠・長岡鉄男さんは、「必要なければ吸音材を使わなくてもよい」ということを、いろいろな機会に書き残されています。 つまり、長岡流の自作スピーカーは、まず吸音材なしで音を聴き、何か難点が耳へ届いたらそれから吸音材を利用する、ということですね。

実は私も長岡さんを師匠と仰ぎ、自ら設計・製作したスピーカーを、長年リファレンスとして使っています。 今わが家でいろいろな試聴や実験に引っ張り出すスピーカーは、数えてみると7ペアありましたが、それらのすべてに吸音材は一切入っていません。
実際のところ、作ってからしばらくは音が落ち着かず、少量の吸音材に頼っていた作例もあるのですが、じっくり鳴らし込むにつれて吸音材の必要がなくなり、全部外してしまいました。
一つには、私がどちらかというと少々の雑味はあっても音の勢いが削がれないスピーカーを好む、ということがあります。 吸音材はキャビネット(エンクロージャー)内部の音を吸いますから、それはユニットから放射される音の素性にも影響を与え、使いすぎると再生音がボソボソと寂しくなったり、情報量が欠けたりしがちなのです。
そこで「これでいいや!」と吸音材を使わずに鳴らしてしまうのは、自作スピーカーの特権といってよいでしょう。 メーカー製のスピーカーは、幅広いお客様の好みへ合わせなければなりませんから、そういうある種 “野蛮” な手段を取ることは難しいのです。
スピーカー自作派の皆さん以外には、あまり役に立たない情報かもしれませんが、吸音材の貼り方というか、効果的な貼る順序を記しておきましょうか。 といっても私の経験的なもので、これが絶対というわけではありませんが。
例えば、フルレンジ・スピーカーユニットを使って、バスレフ型のキャビネットを自作したとしましょう。 吸音材なしで音を鳴らしてみたけれど、やっぱり音に雑味や共鳴が乗って美しくない。 こういう場合にどうするか。

まず、キャビネット内部の後ろ側、ユニットの背面が正対する面に吸音材を貼ります。 それでも音が落ち着かなければ底面、左右どちらかの壁面、もう一方、天面の順番で貼っていくのがいいような気がしています。
ユニットを取り付けている、いわゆるバッフル面はできるだけ貼らない方がよいのですが、どうしても音が落ち着かなければ、ユニットから直接放射される音へできるだけ影響の少ない範囲に貼ることを薦めます。
また、そのキャビネットがバスレフ型であった場合、ダクト開口の周辺へ吸音材を貼ってしまうと、予期せぬダンプドバスレフになってしまう可能性がありますから、注意が必要です。
そこまで貼って、なおかつ音が落ち着かないとなると、これは重症です。 密閉型の解説で申し上げたように、キャビネット内を吸音材で満たすことが必要かもしれませんね。 といっても、ぎゅうぎゅうと押し込むのではなく、キャビネット内寸に合わせて切ったグラスウールを、ふんわりと充填するのが効果的です。

実のところ、スピーカーシステムというものは吸音材不足のみで音がガサついたり、不自然になったりするわけではありません。 特に作りたてのスピーカーで最も大きな原因は、ユニットのエージングが不足している可能性が高いものです。
ということはつまり、ユニットがしっかり鳴らし込まれて本来の実力が発揮できてきたら、初期ほどたくさんの吸音材は必要なくなることが多い、ということです。 前段で解説した通り、私のリファレンス・スピーカーにもそういうものがありました。
メーカー製のスピーカーシステムでは、試作品をしっかり鳴らし込んでから吸音材のチューニングをしているものですから、しっかり鳴らし込んだ後でも中の吸音材を減らしていく必要はありません。 むしろ、そうなって初めて本当の実力が発揮できるようになった、と考えるべきでしょう。
いやはや、意外と書くことが多くてわれながら驚きました。 吸音材も、奥が深いものですね。
Words:Akira Sumiyama
Edit: Kosuke Kusano