鈴木ヒラクは、ドローイングを軸に、その表現の可能性を探り、拡張してきた。描くという行為と、文字や記号との関係を掘り下げ、平面、壁画、インスタレーション、彫刻、映像、パフォーマンスと、多様な表現活動を、国内外で行い、高い評価を受けている。また、2021年より東京芸術大学大学院の准教授として、ドローイングの研究や教育にも携わっている。
こうした鈴木ヒラクの活動のルーツには、音作りがある。音楽家とのパフォーマンスも数多く実践されてきた。インタビュアーである筆者は、若きビートメイカー/サウンド・クリエーターだった彼からデモ音源を受け取ったことがある。それゆえ、このインタビューは、音の話からスタートする。鈴木ヒラクがメインで活動するフィールドは、美術館等の展覧会での作品発表だが、かつての音作りやライヴドローイングからは、現在の表現との繋がりが見えてくる。音と視覚、そして光との関係は、鈴木ヒラクの一貫した表現の核でもある。
音楽を通じて出会った実験映像、そしてアート
僕が最初に話をした時は、音を作っていましたね。90年代後半でした。
そうですね。18歳の終わりか19歳の初め頃でした。元々はバンドをやっていたんですが、高校に入った頃にDJの友達にHIP HOPを教えてもらい、アシッドジャズやトリップホップのムーブメントに影響を受けて、そこからジャズや民族音楽など様々な音世界に興味が広がっていきました。それで簡単な機材を揃えて、自宅のベッドルームで録音を始めたんです。レコードからサンプリングした音をダブミックスして、いつも閉め切った部屋で倍音を響かせていたので、親からは「部屋に水琴窟でも作ったのか?」と言われていました(笑)。また、高校1年の終わりからクラブに通うようになって、例えば当時UFOがやっていたJazzin’というイベントで音を浴びていました。もともと絵も描いていてアートも好きだったのですが、その頃で言うと、画家でありながら音楽活動もしていた大竹伸朗さんの存在は大きかったですね。さらに、音楽を通してアートや映画を知る機会もあり、実験映像にのめり込むようになって。特に好きだったのはデレク・ジャーマンの『BLUE ブルー』で、最初から最後まで画面が青一色っていう映画なんです。それが六本木のシネ・ヴィヴァンで上映された時、サントラを手がけた作曲家のサイモン・フィッシャー・ターナー本人が来日して、行ったライヴには衝撃を受けました。青い光の中でチカチカしているフィルムのキズやホコリと、音の粒子が呼応しているように感じて。そういう実験的な音楽と映像への興味から、武蔵野美術大学の映像学科に入りました。僕の先生はクリストフ・シャルルさんというサウンド・アーティストで、授業ではゲストで大友良英さんが来てノイズについての講義をしてくれたり、刺激的な雰囲気がありました。今ドイツでカーステン・ニコライのメインの助手をやりながら、Raster-Notonから音源のリリースもしているniboも同級生です。
僕が音源を聴かせてもらったのも、そうした背景があって作られたものだったのですね。
当時、僕は、MPC2000というサンプラーに大量のエフェクターをつないで、MDに録音するという方法で音作りをしていました。それで自作を4、5曲入れたデモテープを、国内外のいくつか好きなレーベルに送ったんですが、soup-diskをやっていた原さんから電話が来た時は嬉しかったですね。Compostというドイツのレーベルからもいい返事が来ました。ただ一方で、その頃の自分は音楽制作に行き詰まりを感じてもいました。ひとつの理由は恐らくサンプリングの限界で、もっと楽器の演奏を探究したり、音楽の基礎を学んできていれば違ったのかもしれないと思うのですが、何か同じところをぐるぐる回っているような感覚があって。毎月クラブイベントで音楽のライヴもしていましたが、限られた音素材をサンプリングして再構築するだけの方法では、自分の想像を超えるものを作ることができなくなってきたと感じました。それで10代の終わり頃には、音楽とは別の活動に、グラデーション的に重心が移っていったんです。
その別の活動は、映像だったのですか?
いえ、映像や写真も制作していましたが、当時はそれにも限界を感じていたんです。映像って、基本的にはカメラのレンズやモニターで現実と一枚隔てられているので、その状態から作る行為を始めることにリアリティーを感じられなくなってしまったというか。当時の自分は、まずはその一枚の膜の奥にある現実の手触りから始めないとダメだと感じていたんです。音楽の方はサンプラーを使うのをやめて、フィールドレコーディングを始めました。雨の音や、路上でランダムな音を録ったりとか。そうするとヴァリエーションは無限にあるし、偶然の要素が入り込むから、過去の音楽をサンプリングするところから抜け出せたんです。新宿の地下道で、かっこいいリズムの高周波を出す排気口を見つけたり(笑)。そのうちに、街で音素材を拾ってくるという流れで、音以外のものも拾ってくるようになって。例えば街路樹から落葉した葉っぱと、道路の植え込みの土といった、都市で採取した自然の素材で作品を作るといった方法も試すようになりました。枯葉の葉脈の中心線はカーブしているので、それをつないでいくと円になるということに気づいて。そして、繋いだ枯葉の葉脈の上に一度土を塗って固めて、葉脈の中心線で描かれた線の部分だけを掘り出すという方法で、架空の化石みたいな作品を作り始めました。これが、1999年から2000年にかけて制作した『bacteria sign』(バクテリアサイン)というシリーズです。

枯葉、土、アクリル、木製パネル
金沢21世紀美術館蔵 撮影:斎城卓 © Hiraku Suzuki
環境音を録ることは、現物には触れない行為です。対して、葉っぱを拾うことは、モノに実際に触れる行為ですね。そこに違い、あるいは共通することはあったのですか?
僕にとっては、どちらも身近にあるけどそれまで気づかなかった、微かな響きに耳を澄ませるような行為でした。環境音そのものは実際に体感できますよね。でも環境音を記録して、つまり痕跡化して、エフェクトをかけて再生するように、葉っぱも、そのものを提示するわけではなく、一度埋めてその痕跡を発掘して見せるわけです。ランダムな自然の線の欠片を集めて、繋いで、埋めて、掘り出す、という行程を踏むことで、線を描く主導権が人間にあるのか、人間以外にあるのかが判然としなくなる。もちろん手を動かしている主体は自分なのですが、意図とズレながら形が生まれてくるこの方法は、自分にとってリアリティーがあるものでした。つまり、既にあるものの痕跡に手を加えることによって、何か別の記憶というか、新しい空間や時間を立ち上げることで、それを自分はダブの方法論だと捉えています。『bacteria sign』はいくつかの現代美術系のギャラリーで展示していましたが、それと同時に、それまで音でライヴをしていたイベントの中で、会場付近で掘ってきた土を使って、ライヴで何かを描くということも始めました。
様々なアーティストとの共演、パフォーマンスの実験
そうした手法も使って、90年代末から00年代中盤にかけて、鈴木さんは音楽と一緒に頻繁にパフォーマンスをしてましたね。
そうですね。パフォーマンスは、いろんな人との出会いで続いていった感じです。最初はShing02くんやShuren The Fireといった、革新的なラップをする人達が共感してくれました。それからVJの生西康典さんとデザインユニットの生意気が主催していたイベントに呼ばれて描いたりしているうちに、彼らが西麻布にSuper Deluxeという場所を作り、そこで毎月のように雑多なジャンルの音楽家やアーティストとセッションするようになりました。例えばテニスコーツと出会ってからは何度も一緒にやったし、ダンサーの東野祥子さんや、ガムランとも一緒にやったり。あとはUPLINKという場所の存在も大きかったです。当時は異ジャンルを融合させるような即興の実験が頻繁に行われていて、そういう中で自分は鍛えられてきました。僕自身のやり方も、始めた頃は掘ってきた泥でバーっと描くだけでしたが、マーカーを自作したり、書画カメラとプロジェクターを使って手元の映像を投影するなど、どんどん変わっていきました。
あの頃は、ストリートアート、グラフィティと音楽との関係も活発でした。そうしたムーヴメントとの繋がりは感じましたか?
僕自身は違った道筋で独自に始めた活動が、同時多発的なムーヴメントと重なって、繋がりを感じた時期もありました。それはそれで楽しかったのですが、自分は最終的にはそういうところから離れていったので、簡単ではない思いがありますね。もちろん、ストリートアートから多くのことを学んだとは思っています。例えばゼウスというアーティストが、パリの街にある電灯とかベンチなどの公共物の地面に落ちた影を、アスファルトの白線のような白いペイントでなぞるという活動をしていて、それに刺激を受けました。僕はそもそも地面と関わるアートが好きで。小学生の頃に、父親に連れられてイサム・ノグチ展を見てから、アースワークとかランド・アートと呼ばれるような、アメリカやイギリスの美術に興味を持ってきました。地球自体を素材とする感覚だったり、太古の昔と繋がるような時間的なスケールの大きさに惹かれて。例えばマイケル・ハイザーが地面に巨大な切り込みを入れたり、イギリスだったらリチャード・ロングの、自分が地面に歩いた軌跡の線などです。それらは60年代とか70年代に大自然の中で行われたのですが、ストリートアートの場合はそういう行為を都市の地面に刻んだりする、身近な環境に対してのアプローチがすごくいいなと思っていました。グラフィティも都市の洞窟壁画として捉えられると思ったし。また、僕はバックパッカーをやっていたのですが、旅先の世界中の都市でマンホールの蓋の記号を集めたりしていました。路上のマンホールに紙を置いて、靴で踏みつけながら擦ると、靴の裏に付着した土で、文字や記号が浮き上がってくるんです。僕にはまずそういう道路での体験が大事でした。
ゼウス
フランスのストリートアーティスト。同じくフランスのストリートアーティストのパイオニア、インベーダーやアンドレらと共作するなど1990年代から活躍している。
マイケル・ハイザー
アメリカ出身のアーティスト。ギャラリーや美術館の伝統的なアートスペースから出て、大地や巨岩などを用いてサイトスペシフィックな彫刻作品を制作するランド・アートで知られる。
リチャード・ロング
イギリス出身のアーティスト。ランド・アートをはじめ、インスタレーションやペインティングなど幅広い表現の作品を制作するが、自然と人間の関係性というテーマを一貫して持つ。
何にもカテゴライズされない路上の言語と、川久保玲、アニエス・ベーとの協働
しかしながら、自身の活動はストリートアートの方には向かわなかったわけですね。
僕にとっては昔も今も、作る行為の原動力は、何か特定のカルチャーをリプリゼントすることではなくて、未知なものに触れたいという好奇心なんです。でも当時のストリートアートやグラフィティのシーンで重視されていたのは逆に、如何に同じことを繰り返すか、如何にパッと見てわかるようなシグネチャーのスタイルを作るかでした。さらに、ストリート的なものを記号として利用して、商業的に成功していくような流れが出てきた時に、僕はそこにいたくないなと思ったんです。また、自分の周りに、本物のストリートアートをやってる人たちがいました。グラフィティのレジェンドだとKAMIくんとかが身近にいて、彼らから精神的なところも含めて多くを学ぶと同時に、自分は違うんだなとも気付かされました。
違うとは、どういうところがですか?
色々ありますが、ひとことで言えば、自分は何にもカテゴライズされたくないということですね。どんどん次を作って、自分が作った作品に自分で驚きたいので、常に自分をカオスの状態に保っておく必要がある。そのためには、当時のストリートシーンのように、固定したスタイルを持って、何かのカルチャーの構成員になるようなところからは逃げていきたいというか。逆説的ですが、僕が学んできたストリートの精神というか、路上の哲学を尊重するためにも、周りがどうとかではなく、自分の道を歩きたいと思ったんです。その頃から、自分の言語を作るということを考え始めました。僕はスタイルではなくて、ボキャブラリーを持とうと。それで路上で発見した記号の断片をもとに、1000枚のドローイングを描いて、こういう辞書みたいな本(『GENGA』)を作りました。『GENGA』は「言語と銀河の間」という意味で、これは路上の言語というか、野生の記号集のようなものです。一つだけ決めたルールは、繰り返さないこと。この1000ページに載っている1000枚のドローイングが全部違う、ということが重要だったんです。この本を見たコム・デ・ギャルソンの川久保玲さんからコンタクトがあり、後に協働をしたんですが、彼女も似たような考えを持っていたと聞きました。川久保さんとは、3年間に渡って5回ほど一緒に仕事をしましたが、毎回違う形で刺激的でした。

アーティストとして認められていく中でも、カテゴライズを避け続けてきたと。
自分は、未だに「よくわからない人」だと思います。反射的にあえて逆のことを言ったりやったり、絶対に話が通じなそうなところに行くことが多いです。そうやって周囲とのゆらぎを持つことで、自分の中のカオスを調節しているというか。重要なのは、作品そのものに確信が持てることと、自分にとって新しい何かを作り続けることだけなので。
アニエス・ベーに認められたことがキャリアの転機の一つになったと思いますが、アニエスは、鈴木さんの作品のどこに惹かれたのだと思いますか?
アニエスとの出会いは2005年だったのですが、スーデラ(Super Deluxe)などでのライヴドローイングも食傷気味になってきて、自分が一番中途半端な時期でした(笑)。でも、たまたまアニエスにその頃描き始めていた『GENGA』を何枚かパッと見せた時に、「あなたは子供の頃から文字を書くことと絵を描くことが好きだったでしょう?」と訊かれたんです。アニエス・ベー(agnès b. )のロゴって手書きですよね。フランスという国は洞窟壁画も多いし、アンリ・ミショーのような詩人でありながらドローイングをする作家がいたり、言葉と絵の間の領域に関して凄く深い文化を持っています。アニエスの最初の旦那はクリスチャン・ブルゴワっていう、パリの伝説的出版社の創設者で編集者なんですが、ウィリアム・バロウズの『裸のランチ』を出版した人なんですよ。アニエス・ベーのベーは、最初の旦那の頭文字のbをずっと使っているんです。バロウズがやっていたカットアップによって新しい言葉を作るといった実験に馴染んできた人だから、僕がやっていたことを一瞬で理解してくれたのかもしれません。突然「あなたは私の友達だ」と言われて、ご飯に誘ってくれたので、行ったら、横にジョナス・メカスがいて驚きました。それからファッション・ショーの会場に連れていかれて、ランウェイの後ろでライヴで描いて欲しいと言われたんです。
アンリ・ミショー
ベルギー出身のフランスの詩人・画家。心象風景を表現する詩や、アンフォルメルの先駆けとなるドローイングも発表する。20世紀の文学と美術において独特な存在。
ファッション・ショーで描いたのをきっかけに、海外でやるようになったのですか?
ショーの後、アニエスには2006年にパリに呼ばれて個展をしましたが、それ以前にも2004年にスウェーデンで展示とパフォーマンスをしたり、色々なきっかけはありました。もともと旅が好きで、旅の中での出会いが大きかったと思います。長期的に海外に滞在するようになったのは2009年からで、アーティスト・イン・レジデンスであちこちに行く機会が増えました。ブラジルに2カ月、オーストラリアに2カ月、ロンドンに3カ月、そして2011年から2012年はニューヨークに住んで、その後に2014年までドイツのベルリンに住みました。
点を繋いで線にした「ドローイング」という概念
アーティスト・イン・レジデンスで招聘されるようになったのはなぜですか?
ブラジルの件はスウェーデン人のキュレーターが紹介してくれたり、結構バラバラですね。ロンドンのチェルシーカレッジに行ったのは、トーキョーワンダーサイトという機関からの派遣だったし、ニューヨークはアジアン・カルチュラル・カウンシルという財団だったり。いずれにせよ、自分がそこに行く必然性を言葉にしたら、実現したという感じです。というのも、2007年あたりに、それまで色々な方法で実験してきたバラバラの点が、ドローイングという言葉を当てはめると線でつながることに気づいてきたんです。ドローイングという焦点を持つことで、自分の内側と外側が開通したというか、周りがより見えるようになって。その頃欧米では、コンテンポラリー・ドローイングのシーンというのが発生していて、僕がずっと関心を持ってきた、音とドローイングや、空間とドローイングの関係を扱うような展覧会やアーティストや機関が注目され始めていたんです。日本では全く紹介されていませんでしたが、それが自分が海外に出ていくモチベーションになりました。
話を伺っていると、アクチュアルな活動を続けていく中では、過去から発見すること、振り返って探求することの影響も大きいのではないか、と感じました。
子供の頃から考古学が好きでした。ロンドンでは、エジプトの神聖文字(ヒエログリフ)が刻まれているタブレットを見るために大英博物館にしょっちゅう通っていて、有名なものだとロゼッタストーンがありますが、そういった文字板の形を模して彫刻を制作していました。文字板の表面に、ヒエログリフの代わりに、路上でゆらぐ木漏れ日の光の輪郭をドローイングして、刻んだんです。それで『光の象形文字』という作品を作りました。自分の関心があるのは、単に昔の遺物を発掘することではなくて、そういった考古学的な視点を、今目の前にあるものに適応したらどうなるかということです。普段見慣れているものが突然違って見えてくるような瞬間を、作品制作のトリガーにしてきました。思えば最初からそうで、音楽をサンプリングしていたのも、枯葉を拾っていたのも、結局はそこに繋がります。

サンプリングをしていた時に、音楽の基礎を学んでいればまた違った展開があったのかもしれない、という話も伺ったことがありますが、ドローイングに関しての技術的な部分では何か感じていましたか?
音楽でもドローイングでも、作る上で、何か自分を超えた大きなものと接続する方法があれば、自分の狭い世界の中での堂々巡りを抜け出して進んでいけるんだと思います。そのために音楽の基礎や楽器の技術が助けてくれることもあるはずだったと思うんですが、自分の場合はわかりません。もしかしたらもっと音の根源を辿るように続けていってもよかったのかもしれないと、今では思うこともあります。僕はドローイングに関しては、いわゆる学校で誉めらる上手い絵というか、対象を本物そっくりに描くことによって世界を規定するようなルネッサンス以降の価値観よりもずっと遡って、旧石器人と同じくらいの感覚でやっています。そして古今東西のドローイングの研究をしたり、すごく広大な領域から線を見つけ出すことにフォーカスすればするほど、音に近づいていくのを感じます。ずっと前に、アートに活動の重心が移って少しだけ忙しくなってきた時に、一旦音楽は置いておこうと決めて、機材を片付けたり売ったりしました。でも、ここ最近は、自分がやっているドローイングは音楽と一緒だったなと思うことが本当に多いです。またいずれ音楽制作は再開すると思います。たまに遊びで音楽を作ったりはしていて、2010年には、Test TubeというレーベルからEP(『Beam Drop』)を出しました。ポルトガル人のアーティスト(Rui Gato)と2人で、ブラジルのミナス州にあるクリス・バーデン作の鉄の彫刻を手で叩いて一発録りで録音したものです。
Rui Gato and Hiraku Suzuki EP 「 Beam Drop 」
サウンド・アートの草分けといえる鈴木昭男さんとは、最近も共演されてますね。彼から学んだことはありますか?
昭男さんは一番エコーを理解している人じゃないかと思います。エコー発生装置とも言えるアナラポス(注:オリジナルの創作楽器)は分かりやすいですが、あれ以外でも、演奏するときにあるひとつの音がエコーしてだんだんと消えていく、音の痕跡の部分に耳を開いていくというか。それはコントロールするというのとはまた違うんですが、無音の地点まで意識を引き伸ばして、ちゃんと最後まで音を愛するところはいつもすごいと思いますね。あとは、一般的には音って好き嫌いがあるだけだと言われることもありますが、やはり根源的にはいい音と悪い音というのがあるんだと思います。昭男さんは、小石と小石をぶつけるだけでいい音がする。それが本当に謎ですが、共感もします。
鈴木昭男
1960年代初頭より「聴く」ことを主体としたスタンスで国際的に活動するサウンド・アートの先駆者的存在。創作楽器の制作や、地面のある地点に立ってその場所の音に耳をすませる作品「点音」の発表などを行い、世界の主要な美術展や音楽祭に招聘されている。
オフィシャル・サイトに掲載されている、ご自身で書かれた文章(http://hirakusuzuki.com/texts/)を読みました。表現の言語化に意識的で、言葉がとても大切にされていると感じましたが、言葉を使うことに関しての考えを訊かせてください。
2000年代の前半の頃は、既存の言葉では言い尽くせないことが多すぎるとばかり思っていました。それなら新しい言語を作るしかないと思って、『GENGA』という辞書を作ったりしていました。でも、それは同時に、「言葉とは何か?」を考えることでもあって。ニューヨークで出会った編集者のボニー・マランカに、僕の作品は全て「Post Literature Poetry」(文学が終わった後の詩)だと言われたことがありますが、僕は何かが言葉になる直前とか、直後の状態に興味があるんだと思います。でも人間はただの無意味には耐えられないし、それはそれで繰り返しになってしまうので、言葉から遠く離れることと、それを既存の言葉でも言ってみるといった両極端なことを意識するようになりました。
シルバーのマジック、音と光
現在の作品は、シルバーのスプレーやマーカーを使ったものがメインですね。シルバーにフォーカスするようになった理由を教えてください。
自分の興味が光に移っていった時に、光を反射するメディウムとして、シルバーのインクやステンレスや反射板が作品に出てきました。そう言えば、音と光は、現象として似ていますよね。僕の場合は、大きく言えば、扱う対象が音から光へ移行していったと言えるのかもしれません。光を直接的にテーマとするようになったきっかけは、ロンドンに居た時に木漏れ日が気になりはじめたのもそうですが、一つは人間がなぜドローイングを始めたかという考古学的な興味で、いろんな説があるけど、どうやら必ず光が関わってるらしいというのがあります。例えば洞窟の入り口から入ってきた光の輪郭をなぞったとか、月の満ち欠けを刻んだカレンダー石だとか、星座にしてもそうですけど、闇の中の光を記録することから人間は描き始めたんですね。もともと街を歩いていて、ステンレスの手すりやビルの壁が日光を反射しているのとか、雨上がりのアスファルトの粒が銀河のように見えたり、川の水面に反射する光とかを見るのが好きで、そういうところからドローイングを立ちあげていくことを考えていました。

音と光の関係は興味深いですね。光は電磁波で、圧倒的に速く、波長も短いですけど、光の振る舞いを、音との対比で捉えると見えてくることがありそうです。
作品が反射する光の振る舞いというのは、今日の話でいうとダブの部分です。描かれた痕跡そのものではなくて、それが反射した光を見ている状態は、ダブ的だと思うんです。光の現象によって、描かれた線を時間と空間にエコーさせていくというのが、自分が音作りをしていた時からやっていたダブの方法論とつながっています。ごく最近の作品は黒地にシルバーで描いていますが、表面の黒いテクスチュアは土とアクリルを混ぜたものなんです。そこにシルバーで描くことで、描いた痕跡が穴になってそこから光がこっちに放出しているように見える。白い背景に黒で線を描くというのは、光の中に影をつくることですが、それが反転しているわけです。
描くと共に、削り出す感覚があるということですね。
そうですね。光の粒子を発掘しているというか。描く行為によってレイヤーを付け足して重ねていると言うより、レイヤーを削って、その奥にある光をこっち側に引き出している感覚があるんですよ。あと、シルバーについては(アンディ・)ウォーホルの有名な言葉があって。彼は作品にシルバーを多用したことで知られていますが、「シルバーは私たちの過去でもあり未来でもある」と言っています。ハリウッドの女優は銀幕の前でアクトしていたし、宇宙飛行士はシルバーの宇宙服を着ている。ハリウッドの女優たちは過去で、宇宙飛行士たちは未来だと。そして「シルバーは全てを消し去るんだ」と言っていて、その言葉のこともよく考えます。何というか、シルバーは、現実の物質性を一回消し去って、過去と未来をつないでしまうようなメディウムだと思うんです。2013年にルーヴル美術館の地下で行われた”Drawing Now Paris”では、僕のシルバーの作品が、ウォーホルの手描きのドローイングの隣に展示されたんですよ。
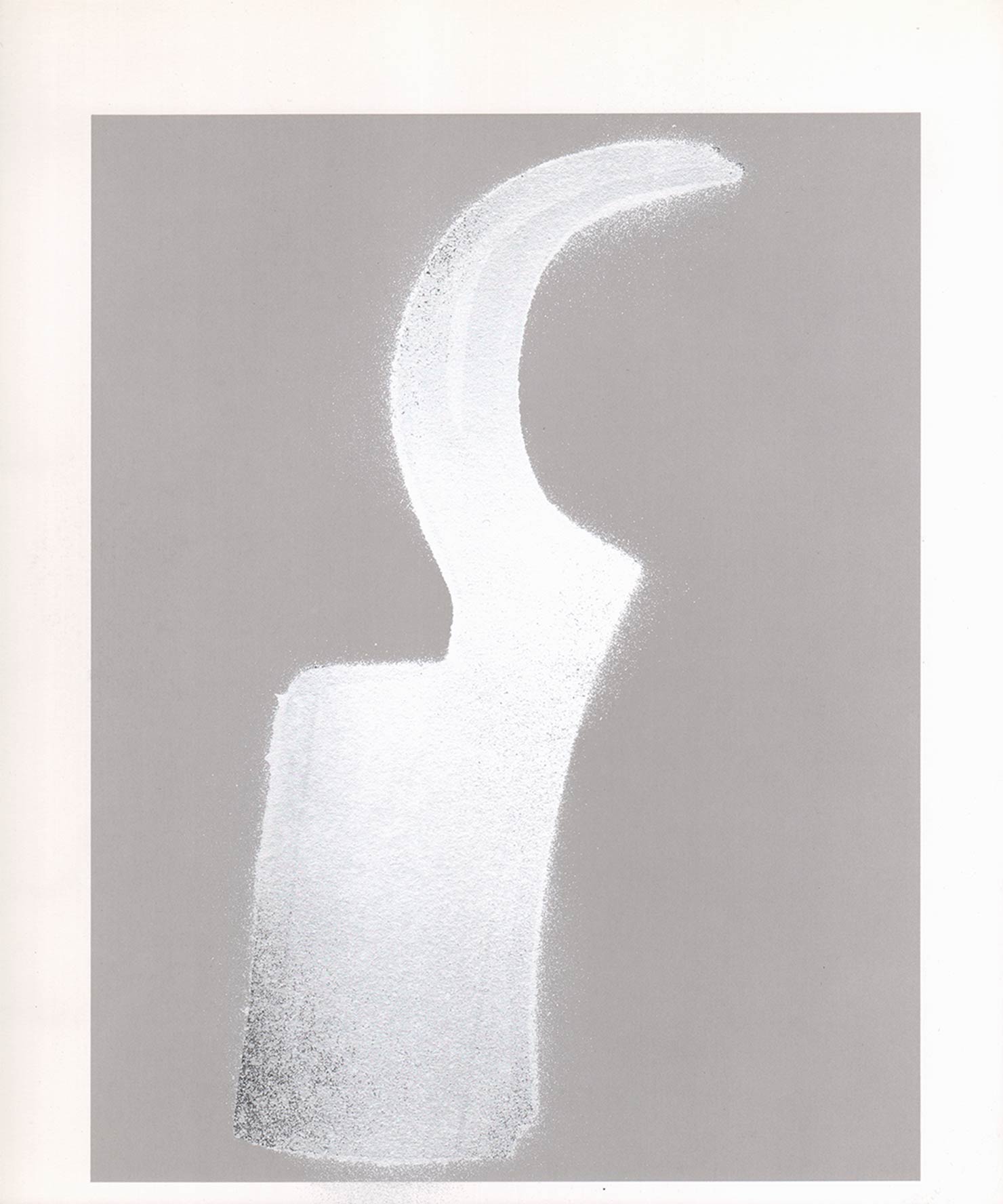
博物館のカタログ切り抜き、シルバースプレー
高橋コレクション蔵 © Hiraku Suzuki
ドローイングであらゆる領域を超え、魂の旅へ
このインタビュー・シリーズで、共通してお訊きしている「超越」について、伺います。「超越」という言葉から、答えられることはありますか?
色々あると思いますが、音との関係でいうと、僕が活動しているフィールドはビジュアルな表現ですが、感覚としては音を作っていたときと変わってないんですよね。リズムだったり響きだったり、音を作っていたときの感覚を、むしろ今の光を反射させるドローイングの方法論で研ぎ澄ましてるようなところがあるので、視覚と聴覚の超越というか、越境の形は、自分の特徴なのかなと思います。それに僕が今まで共演してきたミュージシャンは本当に様々ですが、何かのカテゴリーを越境してきている人が多いです。ラッパー達もそうですが、鈴木昭男さん、ニューヨークで出会ったローレン・マザケイン・コナーズ、ラズ・メシナイ(バダウィ)とか、スガダイローさん、ジェイソン・モランとか、テニスコーツ、カジワラトシオさん、灰野敬二さん、坂口恭平、ハトリミホさんとか、いろんな人とやってきました。その辺は、僕なりの越境の仕方をしてきたからなんだろうと思うんですね。
共演してきた方々も、カテゴライズを回避してきた人達とも言えますね。結果的に、そのような人を選び、繋がっていったのではないでしょうか。
逆に言えば、自分がドローイングをしてなければ、こんな風に巡り会うことができなかった人達だと思います。音楽好きのアーティストはいっぱいいると思うんですけど、ローリング・ストーンズが好きなんだとか、現代音楽の歴史に詳しいとか、僕はそういうことよりは、今現在進行形でどんな音楽が生まれているかに興味があります。それこそ今だったらアメリカ西海岸の人たち、カルロス・ニーニョとかって面白いじゃないですか。ああいう人たちから、同時代に表現してる作り手として影響を受けるんですよ。物理的な越境という意味では、海外に住んでいた時は一ヶ月に10回くらい飛行機に乗って、文字通り色々な国を越境していました。ロンドンのPlastic Peopleというクラブで毎月セオ・パリッシュが回していたので、彼が音の彫刻と言う、まさに立体的な音響を全身で感じたり。インドの暑くて狭い映画館の中で、ぎゅうぎゅうになりながら現地の音楽を聴くとか、メキシコの田舎の教会にひっそり入り込んで、原住民のお祈りのための音楽を聴いたり。その場でしか見られないもの、聴けないものを求めた越境を、2010年代の半ばくらいまでしてたわけです。
それ以降は、物理的な越境を求める必要がなくなったのでしょうか?
確かに今は全く逆のベクトルで暮らしていて、基本的には家かここ(スタジオ)にいる時間が長いです。子供と遊んだり、土に触って植物を育てたりすることが新鮮なんです。地理的な移動によって珍しいものに向かっていくという意識はぐっと減ったのですが、その分、時間的な移動がしやすくなったと言えるかもしれません。海外を飛び回って移動ばかりしていた時には、身軽ではあっても、何かが時間として積み重なっていかないストレスも感じていました。制作にしても、生き方にしても。でも今は積み重ねることができるし、足元を掘り下げることによって、より大きなものとアクセスできるということを知りました。それは自分の内側から思い出すことだったり、身近にあるけど見えなくなっていたようなことに出会い直して驚く瞬間だったり。また、大学で教え始めたので、学生と接する中で自分が20代だった頃を思い出したり。あとは、日本の古層というか、旧石器時代や縄文の遺跡とか、自分のルーツである東北を回ったりもしています。これはこれでいずれ飽きるかもしれないですけど、最近はそういう、忘れていたことを思い出すような出会いが自分にとっての越境です。特に今はこういったコロナ禍の状況で、物理的に移動することが難しいからこそ、見えてくる超越の方法というのがあると思います。今年の3月にも、南フランスにいるアーティストとオンラインで繋いで、同時にドローイング・セッションするというイベントを企画したんです。それもコロナ以前には発想しなかった、新しい超越の方法だったかなと思います。

2021年3月21日 TERRADA ART COMPLEX II(東京)でのパフォーマンス風景より
photo by Ryosuke Kikuchi © Hiraku Suzuki
それが、ドローイング・オーケストラ(https://drawingorchestra.org/)ですね。
ドローイング・オーケストラは、自分がやっていたライブドローイングの進化系で、8人の多様なかき手を集めて、同時に描くというものです。書家がいたり、機械で描く人がいたり、グラフィティ・ライターがいたり。そして、彼らの描く手元の映像をミックスしてスクリーンに投影するのですが、絵だけではなくて、描いている時に出る音もマイクで拾ってミックスすることで、ドローイングを音楽にしていくという実験なんです。洞窟壁画のいくつかは、ドラムを叩くように洞窟の奥の壁を叩いて空間に響かせながら描いていたという説もあるように、もともと描くという行為の始源には音が関係していたわけで、そういう感覚を取り戻す試みでもあります。一回目は東京都現代美術館で行ったんですが、今回の会場は寺田倉庫で配信ブースを組み、アルジェリア系フランス人の(アブデルカデール・)ベンチャマという友人のアーティストとリアルタイムで繋いで、セッションに加わってもらいました。彼はモンペリエにいるんですが、例えば僕が「今モンペリエの空はどんな感じ?」と文字で書き、その文字の上に彼が雲のような線を描いて、僕がそこに雨を降らせて、それが川になって、星が出て、、、といったような感じで即興で進んでいくセッションをしたんです。実験的な映画をその場で作り上げていくような感覚があって、あれは結構、超越していたと思います。コロナの状況ということもあって、アフタートークでは皆で喋る代わりに筆談をしたんですが、寄せ書きみたいになっていった中で、ベンチャマが今回の実験は「Sprit Travel」、魂の旅だったと書いていました。確かに、彼の魂が本当に旅してきているようなことを僕らも感じていたんですよね。新しい時空のトンネルが開通したような感覚というか、それこそが、僕が考えるドローイングなんです。本来はもっとトンネルが開通していてもおかしくない、色々な領域の間の分断っていっぱいあると思うんです。そういうところに穴をあけてチューブみたいな線でつなげることがドローイングだと思うし、それは超越という概念とも関係していると思います。

Words : Masaaki Hara
Photos : Aya Tarumi


