ネルホル(Nerhol)は、田中義久と飯田竜太によるアーティスト・デュオだ。3分間に200枚連写した同一人物のポートレートを印刷して重ね、彫り込んでいった立体的な彫刻作品『Misunderstanding Focus』が彼らの代表作である。その手の込んだリアルなプロセスと、でき上がったマテリアルとしての存在感には圧倒される。ネルホルのアプローチは、ポートレート以外の作品にも拡がっており、丁寧に紙を重ねて彫ることで生まれた断層は、まるでアナログ・レコードのカッティングされた溝を想起させもする。それぞれ異なるフィールドでプロフェッショナルとして活動してきた2人が、個人ではなくネルホルとして共に作ることで浮き彫りにしようとする表現は何か。じっくりと話を伺った。
練ると掘る、見出した互いの接点
—そもそも、なぜ2人で活動を始めたのか、訊かせてください。
飯田:僕はずっと彫刻家として活動をしていますが、2005年に開いた個展を、田中が見てくれました。同じ静岡の出身で、お互い紙が好きで、田中は僕の作品にデザイン的な要素を感じ取ってくれたようで、僕もデザインが好きだったので、彫刻ではなくてデザインのコンペに出していた経歴もありました。初めて2人で会って話したときに、「一緒に作品を作れたら面白いよね」という話になり、小さな作品を作るということから始めました。面白いアイデアも出てきて、いくつかの作品ができました。せっかくなのでこの作品を展示しようということになり、展示会場のキュレーターから展示をするのであれば2人組の名前を付けた方がいいと言われ、ネルホルという名前はその時から使うようになりました。
初めての展示は自分達では手応えがあったので、その展示で共同制作は終わるはずでしたが、美術・デザインそれぞれ関係者から評価を得られず、「この作品は僕らがやりたかったものとは違うのではないか?」と2人で話をするようになりました。自分と田中が見ていることをしっかり定着できるような作品・プロジェクトがもっとできるのではないかと…。そこから3〜4年ほど、様々な試作品を作りました。そんな中で写真をスタックして彫る方法を見つけ出し、ポートレートの作品『Misunderstanding Focus』という作品ができ上がりました。その作品が僕らの制作の起点になったと思います。
田中:大体、今の話で5年分ですね(笑)。

—なるほど(笑)。2人でやるというのは、1人では足りないものがあったということでしょうか?
飯田:最初はそれぞれの力をただ合わせることを目指していて、その結果どうなるかわからないという不安もありました。現在の制作のスタイルの方が、作品に何かが足りないという感覚が強くあります。お互いを掛け合わせる感覚が今の方が強いと思います。
ジャンル、フォーマット、分断したのは我々ではなくて、もともと一つ
—音楽ではジャンルによる音楽的な言語があって、そこを超えたコラボレーションではすり合わせ、対話が必要になってきますが、彫刻とグラフィックデザインの間ではいかがでしょうか?
田中:“美術”と規定される枠の中でも、対話って作法、文脈が全然違うので難しいです。ですので、グラフィックデザインと彫刻となれば尚更ですよね。それは当然わかっていたことなんですけど、何か共有できる感覚があったからこそ一緒にやってみようってなったと思います。前提として違うというところから入っていくと、共通、共有、共同が可能な場所をすり合わせていく話になってくるんです。僕らは共同制作を始めて13、4年位経ってますけど、まだ全然わからないことが普段からあります。例えば“深さ”という言葉一つ取ってみても、視覚伝達的なアプローチと彫刻的なアプローチで全く違いが出てきます。だからこそ、お互いすり合わせていくことに意義があると思っています。
—各々の個人としての活動もやられていて、2人でやる活動とのバランスはどうなのでしょう?
飯田:時間的配分・モチべーション・バランスなど完全に分ける感覚ではなく、常にそれらは混じり合い、1人でやることと2人でやることは同じ路線にあると気づきました。2人で制作し始めてから、自分個人の彫刻的作品も変わったのがわかります。それぞれが新しい方向に向くと、ネルホルの作品も少しずつ変わり、さらに新しい作品ができ上がる。作品に取り込む素材や方法も変わっていく。そうやって常に変化があり続けるという感覚はあります。
田中:分断したのが我々ではないなというのがあって、飯田が言っていたことって、つまり並列で物事は動いているということなんですよね。家に帰ったら家でやるべきことをするとか、この場所ではこれをやるというように規定をつくるのではなく、常に思考を等しく回転させていくと思いもよらない発見があったりする。それぞれの歴史背景から、強固に積み上げられた違いに対し、間を切り取って繋げていく作業をしているような実感があって、今後はより一層感覚を研ぎ澄ませていきたいです。
—もともと一つというのは、音楽の世界でも近代以前に遡った際に言われることで、そこから現在の細分化されたジャンルを捉え直して、新たに繋がっていく表現を模索する動きもあります。それに近い考えもあるのでしょうか?
田中:あると思います。例えば、決められた体裁を敢えて享受した上で、今後どういう風にアレンジするかと考える方もいるでしょうし、そもそもの根幹を辿っていく中で、他者の感覚との共有を図り、それらを接続していく人もいるだろうし、様々なパターンがあっていいと思うんですよね。私に至っては一度自身の身体で感じたり、継続的な作業が必要で、そうしないと相手のことを理解することができないんですよ。なんとなくの外側からの意見っていうのは言えなくはないのですが、自身に置き換えて寄り添う形で話を聞くとか、会話を実際にするのが、今一番必要なのではないかと考えてますね。そうしないと、簡単に協働とはいかないと思うんですよ。
—一緒にやっていくことで、文脈やシーンの違い、本来別々に成り立っていて良しとされていたこともあぶり出されて、大変なこともあったのではないかと思うのですが。
田中:確かに大変ですよ。ですが、1人で乗り越えられることって限られているんじゃないかなとも思います。深く自分で掘り下げていく行為、何か自分で探求したいという気持ちも持っていますが、それだけだとどうしても範囲が狭まって、結果的に変化を促す範囲すら狭めてしまうことがあると思うんです。いかに他者と共有していくか、一緒に問題を解決するよう努力できるかが重要だと思います。おそらくこれだけ続けられているのは、自分が求めているものを他者によって埋めてもらっているような行為なのかもしれません。
飯田:自己探求的に、新しいエッセンスを取り入れようとすることは、結構大変だと思います(笑)。恋愛と一緒で、その人が好きだからわかろうとしているのであって、好きじゃなかったらその人と関わりたくないし、どうでもいいやと思ってしまう。
田中:我慢になるよね。
飯田:そう思います。それを超えるきっかけとして、何か一つのことだけをやろうと決めている事と、もう一つは相手も同じように一つのことをやっていると思うことが大切だと。分野が違ったとしても、見えてない相手の時間や空間を想像して自分の行動に反映し、自分だけがやっているという感覚にはならないようにすること。全然考えは違いますが、純度の高い思考性も行動も、他人と同じではないと思えた瞬間、尊敬も手助けもできる。もっとその人のことを知りたいと思ったり、何を考えているのかを知ろうとしないと、逆に自分も同じように振る舞えない。結成当初、田中に「お前俺のこと全然興味ないだろ」って言われたことが結構ありました(笑)。すごく反省しています。
田中:飯田は人の名前を覚えないんですよ。私の名前も何年も覚えなかった(笑)。
飯田:当時、自分のことで精一杯で、余裕がありませんでした。そういう状況を作ってしまうということは、しっかりネルホルのことを考えてないとも言える。しかし作ることは真剣でした。その作ることも自分の範疇でしか考えられず、広げて考えられない状況でした。ここ数年もっとネルホルのことを考えるようにしています。すると自然に自分に余裕が出てくるようになりました。

アーティスト・デュオという活動スタイルと世界
—もともと違うジャンルにいて、ネルホルのように一緒に作品を作るアーティストは増えているのでしょうか?
飯田:海外だと結構2人組のアーティストが多いですけど、日本だと少ないですね。
田中:最近はコレクティヴや、複数の人で場所を共有して制作していくのはありますね。次の『ドクメンタ』(※1)のディレクターがアジア圏のインドネシアのチームなんですけど、10人ぐらいの集団で、アジアで選ばれるっていうのも初めてですし、コレクティヴで選ばれるのも初めてなんじゃないかな。日本だと、前回の『ヴェネチア・ビエンナーレ』に美術家、作曲家、人類学者、建築家のコレクティヴで参加してますし(※2)、最近はそういうの増えてるかもしれないですね。
※1 ドイツのヘッセン州にある古都カッセルで1955年より5年に1度開催されてきた現代美術の大型グループ展『ドクメンタ』。2022年に行われる『ドクメンタ15』の芸術監督を、インドネシアのアート・コレクティヴ、「ルアンルパ」が務める事が決定している。
※2 第58回ヴェネチア・ビエンナーレ国際美術展(2019年)の日本館で、美術家の下道基行、作曲家の安野太郎、人類学者の石倉敏明、建築家の能作文徳がコレクティヴとして作品『Cosmo-Eggs|宇宙の卵』を発表。
引用元:https://2019.veneziabiennale-japanpavilion.jp/
飯田:特に日本文化の中では、アーティストのイメージとして個人の名前が強く出ていたかもしれないですね。作品と個人名が必ず結びつく。音楽は1人ではできないからグループだったりしますし、わかりやすく個人と集団が作品上、分断されていないように思います。同じ音楽としてどちらも味わえるような。
—海外に向けての活動はどのように考えていますか?
飯田:デビューできたのは、海外の評価が先にできたことかもしれません。
田中:ポートレートの作品をインターネット上で発表したところ、初めに反応してくれたのは海外が多かったんです。それで、その後からちょっとずつ日本でコレクターの人たちが気にしてくれたりして。純粋に作品がそのまま勝手に広がっていった感じですね。最初のほうは世界中からいろんな依頼が来てはいたのですが、対応できないままその波は終わって。ちょっと落ち着いたあたりから、実際に海外で展示させてもらう機会もいただきました。
—日本と海外の展示で違いはありますか?
田中:物理的に障害が結構あって、作品がとても重いのでシッピング(送料)にめちゃくちゃお金がかかって、そういうのもばかにならないって痛感しましたね。
飯田:しかし逆に物質性を持つ作品の強さを感じました。オランダの写真美術館で個展をやった後は、色々な人からいい言葉をいただけました。初めての海外の個展がオランダのアムステルダムだったのもよかったのかもしれないです。ヨーロッパのいろんな人たちが見に来ている中で発表できたという実感がありました。
写真ではない、作品の物質感
—ネルホルの作品には物、物質としての力がありますね。
飯田:そうですね。音楽で言うところの生で演奏するという感覚に近いと思います。まず身体で体感するのは重要だと思っています。音を耳で聞かずに腹で聞くような感覚。目で見ずに体感で感じてもらいたいと思っています。
僕らの制作方法も2人別々のアトリエでやるので、僕が制作しているものを撮影し田中に送り、2人で相談しながら制作を進めているのですが、写真の平面性によって、深さや立体的なものが凝縮されてしまい、その部分を立体的に把握できません。写真で見た時の良さが、立体で見た時にあまり良くない状況だったりもします。しっかり作品の前に立ち、感じることが大切だと思います。立体を認識することはそもそも僕らの脳が何とかがんばって処理していると思います。平面的である中のすごく微細な立体性があるというのは、僕らが写真を見ているときに欠損させてしまう要素なのではないかと、最近感じています。
—コロナ禍もあって、特に海外に見せるには写真でないと難しいと思いますが、アプローチで工夫することはありますか?
飯田:作品が移動できない以上、作品を撮影した写真で、立体作品と同じ強度を保たせるしかないと思っています。写真で作品を見た時の感覚より、作品に対峙したときの感覚がさらに強くなっていたら嬉しいです。それぞれのメディアでそれぞれ同じくらいの強度を保つ作品であれば良いと思います。写真は写真としてのメディアを面白いと思ってもらえれば。音楽と同じように、レコーディングされたものが良くても、やっぱりライブは違うと、みんなわかっているからライブに行く。そのメディアの違いを楽しむ方法があると思います。
田中:平面的なヴィジュアルが先にインターネット上で広がっていったので、ある種の閉じられた鑑賞体験が先行していったときに、ネット上でしかできない行為があることにも気づいてその魅力も感じたのですが、やはり一番自分たちがやりたいものが凝縮されているのはモノとしてのあり方だなと。なので、それで琴線に触れられないんだったら仕方ないし、僕らは割り切っています。空間でちゃんと身体的に体験すると、様々な変化を人間はキャッチできるんですよね。
—実際、お2人の後ろにある作品は物として圧倒的な存在感がありますね。

田中:重そうとか、大変そうとか(笑)。
膨大な創作プロセスとそこにある可能性
—ちなみに、この作品はどれくらいの手間、時間が掛かっているのでしょうか?
飯田:出力するのが凄く大変です。1枚1枚違う写真を印刷しているので。
田中:これはシークエンスなので、全て違う画像なんです。それが150枚ぐらい重なっているのですが、1枚ずつインクジェットで印刷するので、単純に出力作業だけでも100時間とかかかりますね。その後でようやく彫り始めるので、1ヵ月ぐらいはかかります。絵画と違うところは、彫りすぎるとなくなってしまうんですよね(笑)。なくなっちゃったら、もうダメで、もう1回刷り直そうと。そういうところではオリジナリティーというか、誰もやらないものですね、あまりにも辛いので(笑)。
—音楽との関係もお伺いしたいのですが、サカナクションのアルバム『834.194』(※)のアートワークをやられてましたね。

田中:いろんなお話を聞かせてもらいながら、やりとりを進めていく中で、明確なビジョンが一郎さんに出てきて、それに対して僕らも共感できる部分があったので、どっちかというと作品の提供というよりは、コミッションという形で始めたんです。
サカナクションは北海道出身なので、サカナクションがスタートした北海道のスタジオと東京のスタジオを海で繋ぐっていう話になったときに、僕らは時間軸を水面から海底までを撮影するという行為に切り替えて、北海道の海にカメラを投げてずっと撮り続ける、それと東京のレインボー・ブリッジの(山口)一郎さんがよく釣りをする場所にもカメラを投げて撮影したものから彫ったんです。
飯田: 北海道の海は青く、底に行くにつれて凄く濃い青色になっていきました。彫っていても面白く、東京の海は深くなっていくと、どんどん燻んでいく。
—単にアートワークを担当したというわけではなかったのですね。他に音楽と繋がった仕事はありましたか?
田中:蓮沼(執太)くんが『ミュージック・トゥデイ・トーキョー』(※)というイべントをやっていた時に、パフォーマンスをさせてもらいましたね。石田尚志さんという素晴らしい美術家がいらっしゃるんですが、一緒にパフォーマンスをして、蓮沼くんが音を付けるというのをやりました。
—パフォーマンスでは何をやったのですか?
飯田:石田さんはすごい速さドローイングをしていて、田中がそのドローイングをスタックしたり、破いたりし、自分はその場でそれらを彫る制作をしました。すごく楽しい時間でした。僕は作品を作るので、制作はパフォーマンスと思わないでやっていますが、人が見ていると違う動きになっていたように感じます。
また即興的に動くことができたことも経験になりました。大学院に在学していたときの補助テーマが“インプロヴィゼーション”だったので、“即興と型”というのが当時の制作のテーマになっていました。ジャズ・ピアニストの山下洋輔(※)さんを紹介した授業や、「フリー・ジャズの起源は型だ」と木幡和枝(※)さんが言っていたのを思い出します。即興を練習し続けるから即興性があるんだと。常に即興的にやるのではなく、毎日良いと思うものを続け、自分に実装しておくことが土壇場の即興につながり、面白いものが出来上がる。それはいろんな分野に共通していると思いました。自然なパフォーマンスがすぐに出していくことができたのは、制作を続けてきたからだったのだと、その時に思いました。
(※)木幡和枝
—ネルホル、あるいは個人として、このインタビュー・シリーズの共通テーマ「超越」について、伺えますか?
飯田:作品を作っている時、個人とネルホルで違うところは、終わりが突然やってくるところでしょうか。急に終わる時もあれば、一向に終わらない時もあり、そんな終わらない状況が1ヶ月くらい続く時もあります。つまり、自分の許容の範疇を超えているということです。予測していることを常に超えてくる。自分が「いいな」とか「こうしたいな」という部分ではないところに、必ず2人でやっている価値があると考えています。逆に超越しない時というのは、自分の思い通りに全部できることかなと思いました。
今まで田中のことを分かろうとした時期がありました。それは田中のことがもう少しわかれば、自分のやりやすいようにやれるのではないかと思っていたからです。しかしそれは違うと最近さらに感じるようになりました。自分で良し悪しを決めるのではなく、対話の中で、価値を練り上げ、その中で自分が思いきり制作できることが常に超越的なことだと思っています。
人には時間感覚が実装されているので、時間とともに必ず良くなるという上昇の錯覚があると思います。しかし時間が進むことによって退化することもあると思います。その退化してしまう部分をどうやって手に入れるかっていうことが超越だと思っています。自分で決められないことを増やすことかもしれません。なかなかうまく言えませんが。
田中:確かにそういう感覚はよくわかるところがあって、どこまでアマチュアでいられるかがとても重要だなと思っています。ネルホルやって13年位、デザイナーとしてだったらもう20年以上やっていて、過去の自分のやりやすさとか経験からの自信、あと過去にやったことがあるから反復できる行為とか、そういうのがあるとどんどん軽やかに動いていけるんじゃないかっていう感覚に陥ると思うんですけど、それは更新ではないと思うんですよね。過去のタイミングだからそれでよかったのかもしれないけど、2021年1月現在に当てはまるわけではないから、自分が培ってきた経験に頼りすぎず、常にアマチュアの精神でずっと向き合うっていうんですかね、なるべくトライする、なるべく何かわからないことがあれば理解する、会話する、試してみる。そう続けることが、僕にとっての超越だと思います。
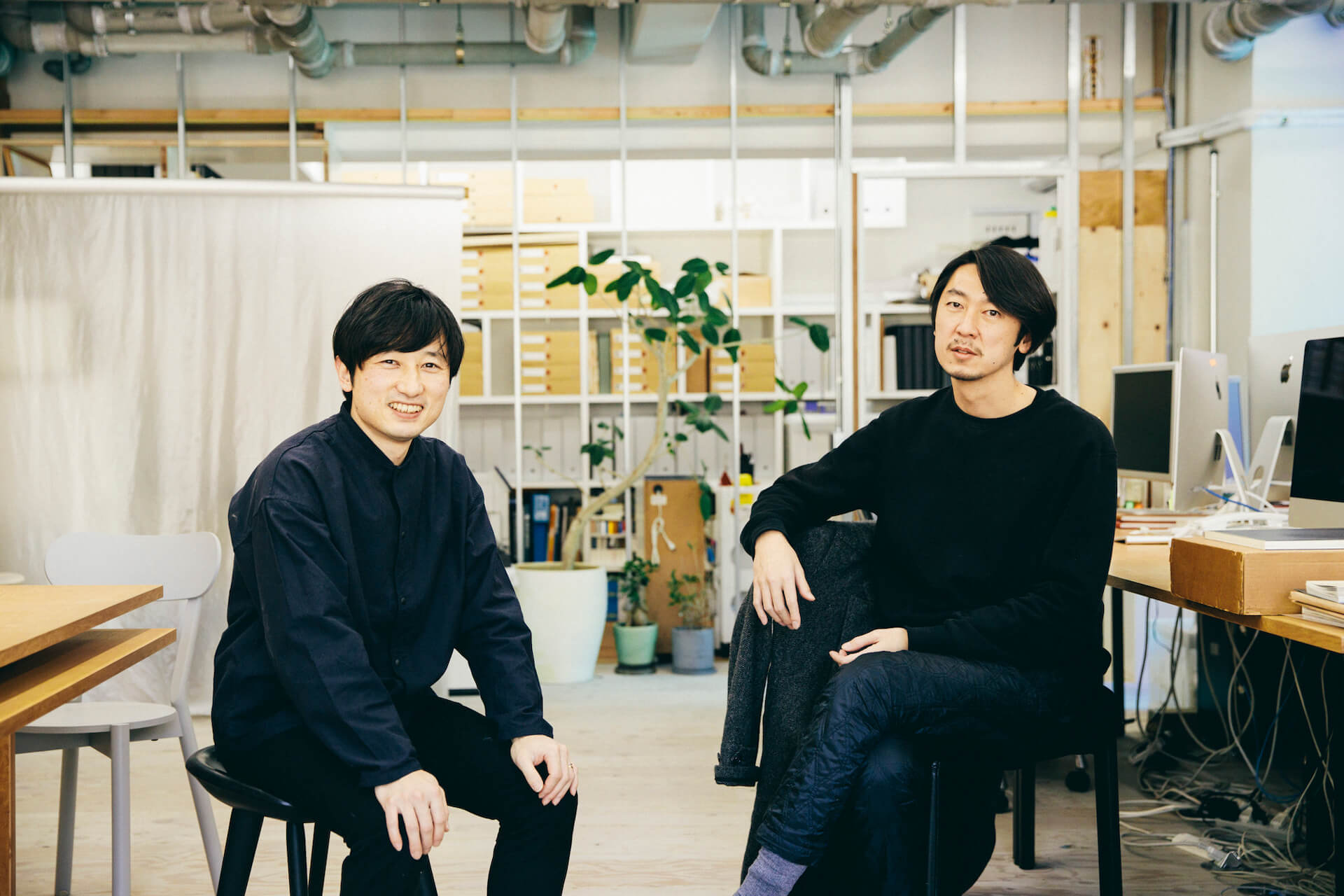
Words: Masaaki Hara
Photos: Aya Tarumi


